ずとまよのファンクラブ会員限定アコースティック・ライブ『コズミックどろ団子ツアー』。その千秋楽のひとつ前の公演を東京ガーデンシアターで観た。
平日にライヴがある日は仕事を休むのが習慣なのだけれど、この日は諸事情あって休みがとりにくい状況だったのと、通勤先の隅田川沿いのオフィスビル前から出ている都バスに乗れば、一本で会場へ行けることがわかったので、仕事を早退して観にいった。いくつもの橋を渡るバスに乗って、馴染みのない下町の風景を眺めながらライブに向かうというのも、なかなかおつなものだった。
ずとまよのアコースティック・ライブはこれが第三弾で、最初がビルボードライブ(チケット取れなかった)、二回目がZeep DiverCityときて、今回は東京ガーデンシアター。しかも全国二十五公演。人気のほどがそのまま公演規模の変化に表れている。
でも今回はこの広い会場が仇になった。
アコースティックセットってことで、終始しっとりとした雰囲気で照明が暗めだったこともあり、最上階に近かった僕らの席からは、ほとんどステージが見えない。
ずとまよ名物の凝ったステージセットも、中央に巨大なタマネギみたいな形のフレームに乗った天体図が配されていたのはなんとなくわかったけれども、ディテールはまったく識別できず。天体図の輪っかの一部で赤いランプが点滅していたけれど、それがなにを意味しているのかもわからない。なにより上から見下ろす形だったので、そのセットの中央にいるACAねがほとんど見えないのがダメージ大だった。
東京ガーデンシアターというと、以前アリーナ席の後方でずとまよを観たときにも、前の人が邪魔でステージがよく見えなくてストレスだったし、ボブ・ディランも照明が暗すぎてまったく見えなかったし、なんでこんなに見えないの?――って経験ばかりさせられている。帰りは帰りで、動線を規制されて、駅に着くまで三十分も歩かされるし。ほんとこの会場は毎回やたらと印象が悪い。
とにかくこの日のライヴも見えなさのせいで楽しさ半減だった。もとよりアコースティック・セットってことで期待度がいつもより低かったうえに、視覚的にもストレス過多ではなぁ……。
ずとまよはACAねが顔出しNGだから、見えなくても関係ないように思えるけれど、顔が見えないのはともかく、動きも見えないとなると話が違う。せめてもう少し照明を明るくするか、スクリーンを配して欲しかった。
そういう意味では今回のツアーは会場規模と演出がミスマッチだったと思う。少なくても席がよくないと十分には楽しめないステージだった。
ライブ自体はアコースティックってコンセプトゆえ、いつもよりスローでシリアス度高めな内容。バンドメンバーはギターに菰口雄矢、キーボード岸田勇気、ドラム(パーカッション?)神谷洵平に、オープンリールの吉田兄弟という構成だった。前回はギターとピアノだけだったから、人数は倍増している。
ライヴは「コズミック」と「アコースティック」というキーワードから連想する曲といえば、まずはこれっていう『サターン』でスタート。最初はACAねの弾き語りで、アウトロから菰口、岸田、神谷の三人が入ってくるアレンジ。
最初の数曲はこの四人だけの演奏で、その後、どの曲からか忘れたけれど――『グラスとラムレーズン』あたり?――吉田兄弟が登場してからは、なにやら重低音が加わって、音作りが重厚になる。あれはオープンリールの効果なんすかね? なんか不思議な音のボリューム感だった。
いずれにせよ、アコースティックな編成ゆえのアレンジの違いがこの日のなによりの聴きどころ。『永遠深夜万博』につづいてスローバラードとして演奏された『クズリ念』とか、意外性のあるスローなボサノバ調の『微熱魔』とか。アンコール〆の『花一匁』も前半部分が超スローでエモかった(若者言葉を使ってみるやつ)。かって知ったるイントロが、いつもとは違うリズムや音色で鳴り始めるのがとても新鮮だった。
まぁ、暗さについて文句をいってしまったけれども、今回のツアーはACAねが深夜にひとり部屋で音楽を作っているシチュエーションを再現する、というようなコンセプトだったらしいので、照明を明るくできなかったのは致し方ないんだろう。でもだとしたら、せめてスクリーンは用意して、ディテールを映像として拾うとかして欲しかったなぁ……。
あとね。全体的にシリアスな曲とアレンジばかりだったので、そこに差し込まれた吉田兄弟の余興が余計。
それが楽しくて好きって人もいるんだろうけれど――というか、ACAねをはじめとした当事者たちは好きでやっているんだろうけれど――音楽至上主義の僕にとっては毎回余計すぎる。そんなことしている暇があるのならば、その分もっと音楽を聴かせてくれって思ってしまう。なまじこの日のステージはなにやってんだか見えなかったので、なおさらだった。素人の笑えない余興ほど寒いものはなくない?
俺がエレカシが好きなのは、宮本がステージでほとんどしゃべらないからってのも大きいよなって思った。
アコースティック企画では恒例の特選カバー曲は、意外や、中森明菜の『スローモーション』――と『黒猫のタンゴ』改め『味噌ネコの団子』のメドレー。『スローモーション』ではサビの最後の部分で「え、なにその歌い方?」と思ってしまうような、演歌的なコブシの効いたボーカルに驚いた(うちの奥さんは「ねっとりしていた」と表現してました)。
すっかり定番となった三曲ランダムセレクション即興コーナーは、どろ団子の専門家(なにそれ?)の大学教授をステージにあげて、一緒にどろ団子を落として割れた方から出てきた曲をやるという趣向で、選ばれたのは『低血ボルト』だった。でも今回のこの曲は即興アレンジのためにACAねの出した指示がなんだか要領を得ず、その通りの演奏になっていたのかもいささか疑問。でもまぁ、大好きな『低血ボルト』が聴けたのは嬉しかった。
そういや、今回はアコースティック・ライヴだから、しゃもじクラップはなしでお願いしますという話で、ツアーグッズのしゃもじもいつものように二枚セットになっていない一枚だけの特別仕様だったくらいなのに、それでいて座って観ていると、たまに「立ってもいいよ~」とか言われて(半ば強制的に)立たされる。結局アンコールも含めると三回くらい立つことになった。
ベース抜きでの『TAIDADA』とか、ちゃんとダンサブルに成り立っているのすげーとか思ったし、立つコーナーは曲がアッパーなこともあり、照明が明るくなって、いちばん観やすかった。でも立ったりすわったりめんどくさいので、どうせならばずっと座ったまま見せてくれたほうが嬉しかったかなぁ……。
というような感じで、今回のライヴは僕がこれまでに観たずとまよのライヴでは、残念ながらもっともマイナス要素が多かった。
ほんと吉田兄弟の余興はいらないんだよなぁ……。あれが今後もつづくのならば、チケットもどんどん高騰しているし、もうそろそろずとまよのライヴとも距離を置いてもいいかなと思ってしまった。
いやでもアンコールではひさびさに大好きな『過眠』も聴けたし。菰口くんのアコギのエッジーな音がとてもカッコよかったし、演奏は文句なしなんだよなぁ……。
というような今回のツアー。暗さもあいまって気が散って集中しきれなかった感があるので(やっぱ仕事帰りなのもよくなかった気がする)、音源が配信されたら、それはそれで嬉しいかもしない。でもって、もし生で聴いていなかったら、それを聴いてライヴに行かなかったことを後悔するのが想像に難くない。ならばあとで後悔するよりは行って文句をいっている方がいい。
――ということで、この先いつまでつづくのかは不透明になってきたけれど、ひとまず来年以降も僕らのずとまよ行脚はつづく予定。
次は二月末の日本武道館だっ!
(Jan. 4, 2026)

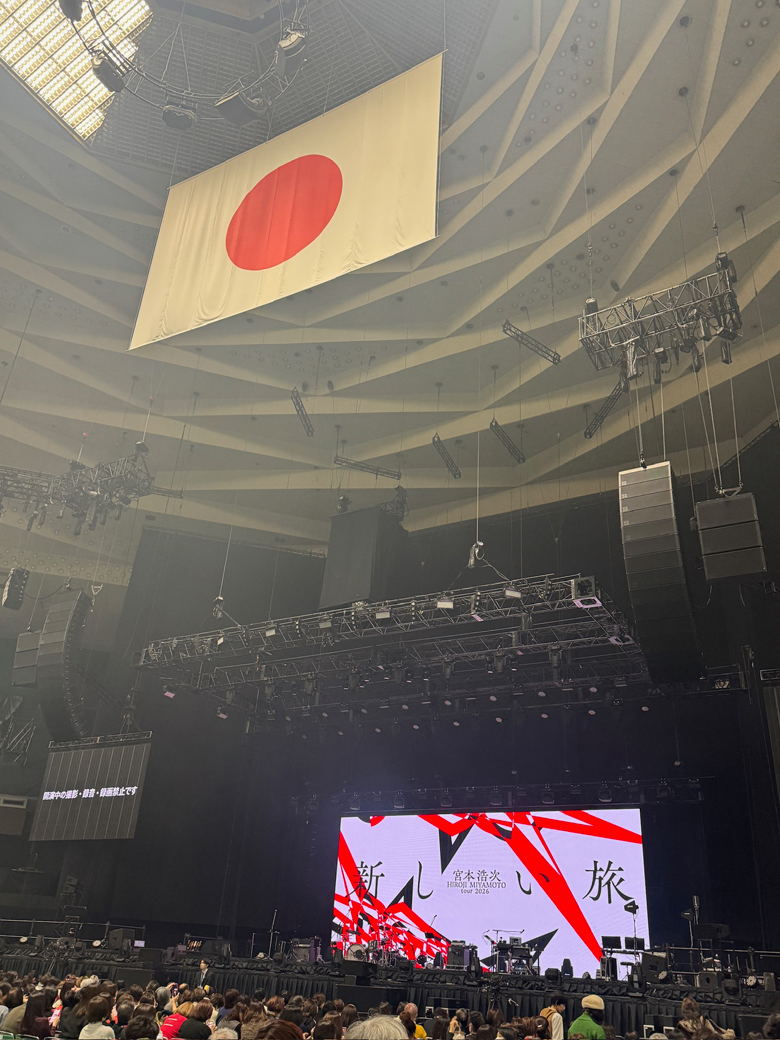



![THANK YOU SO MUCH [完全生産限定盤A] [CD + SPECIAL DISC(Blu-ray) + SPECIAL BOOK]](https://m.media-amazon.com/images/I/31lUeJwQ90L._SL160_.jpg)