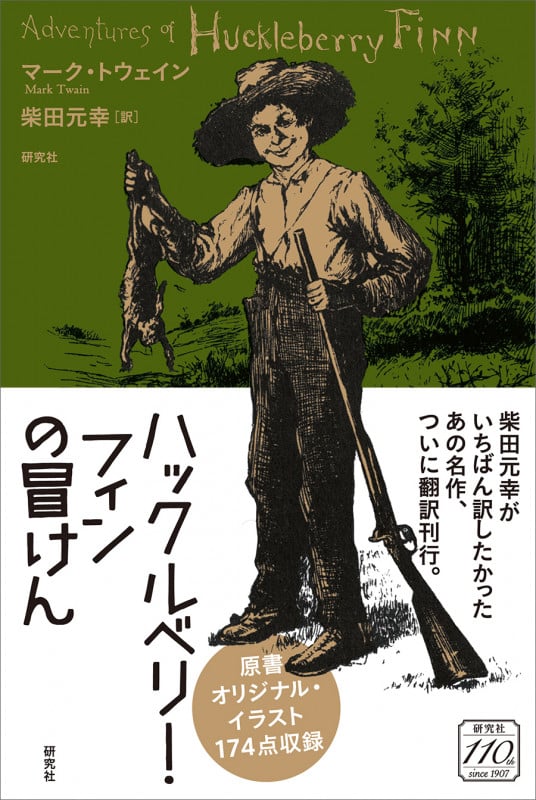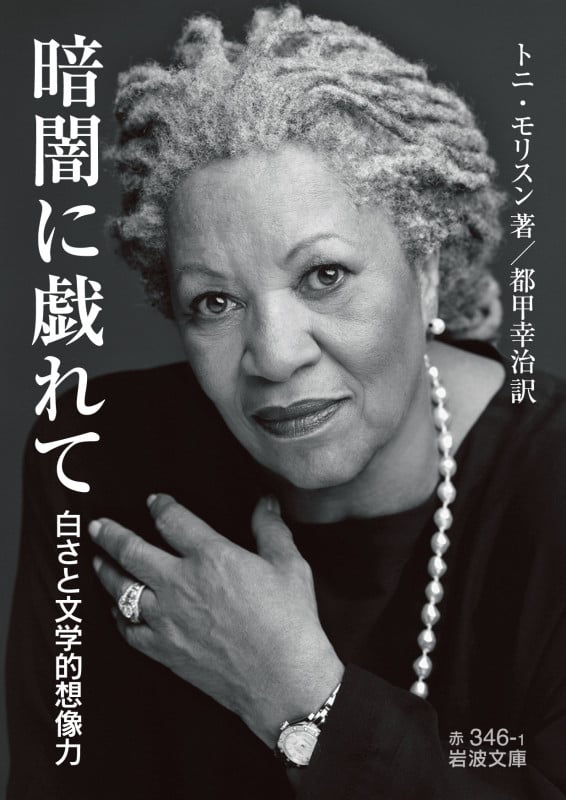ハックルベリー・フィンの冒けん
マーク・トウェイン/柴田元幸・訳/研究者
最近話題の『ジェイムズ』に興味があるので、それを読む前に、せっかくだから長いこと積読に入りっぱなしだったこれを読んでおくことにした。
アメリカ文学史上最重要作とも目されるマーク・トウェインの代表作の柴田元幸氏による新訳版。
語学力が小学生低学年レベルのハックルベリー・フィンによる語りを日本語で再現するにあたって、柴田先生はできる限り、難しい感じは使わないという方針を貫いている。
その点はおそらくほかの翻訳家の手による旧訳でも似た傾向だろうと思うんだけれど(僕が過去に読んだのは岩波文庫版)、決定的に違うのはその漢字の使い方。
『ハックルベリー・フィンの冒けん』という題名にそれが顕著に表れている。
「冒険」でも「ぼうけん」でもなく「冒けん」。
「冒険」という熟語はハックが使うには難し過ぎるけれど、「冒」くらいは漢字で書けそうなので、あえて「ぼうけん」と開かず、「冒けん」とする。
「書ける漢字は漢字で書いたほうが頭よさそうじゃん?」という子供っぽさの表れとして、なるほど、確かに子供ってそういうところあるよねとは思うのだけれども。
結果としてできあがった翻訳の読みにくいのなんの……。
「未亡人」が「未ぼう人」、「利子」が「利し」、「判事」が「判じ」、「時間」が「時かん」――そんな調子で全編が統一されている。
こういう漢字の開き方をした文章が、ここまで読みにくいとは思わなかった。
一人称が「おら」だったり「おいら」だったりする旧訳に比べて、「おれ」を採用した柴田訳は、語り自体はとても現代的な感触でさすがなのだけれど、とにかくこのブロークンな熟語の数々に最後まで慣れることができなかった。
とにかく僕にとってはこの翻訳は文体がすべて。
そんな独特の語りを楽しもうって余裕と心意気がある人には薦めの逸品です。
(Oct. 1, 2025)